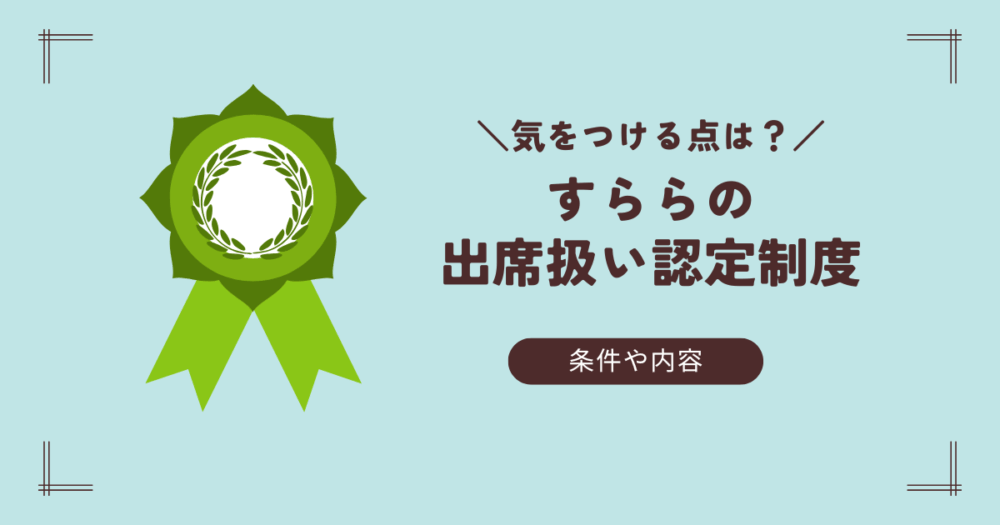「すらら 出席扱い制度 仕組みを知りたい」
「すらら 出席扱い制度 不登校でも使える?」
「すらら 出席扱い制度 注意点をまとめて知りたい」
すららの出席扱い制度は条件が複雑で、何から確認すべきか迷いやすいですよね。
すららの出席扱い制度を利用する際には、学校との合意形成や学習履歴の提示など押さえるべきポイントが複数あります。

この記事では、すららの出席扱い制度の基本、注意すべき点、利用の流れを分かりやすく解説します。
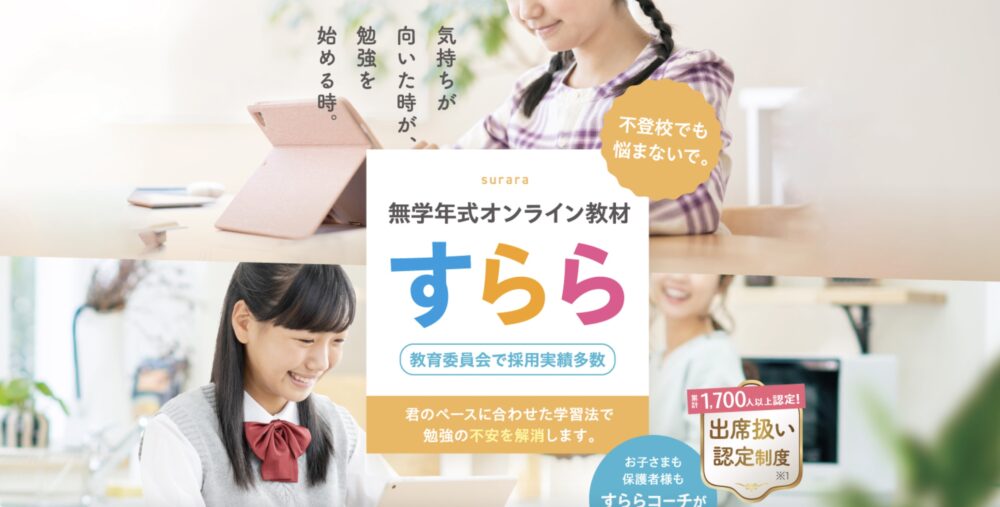
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えます。
すららで出席扱い(ネット出席)をしましょう。
すららの出席扱い制度とは何か?
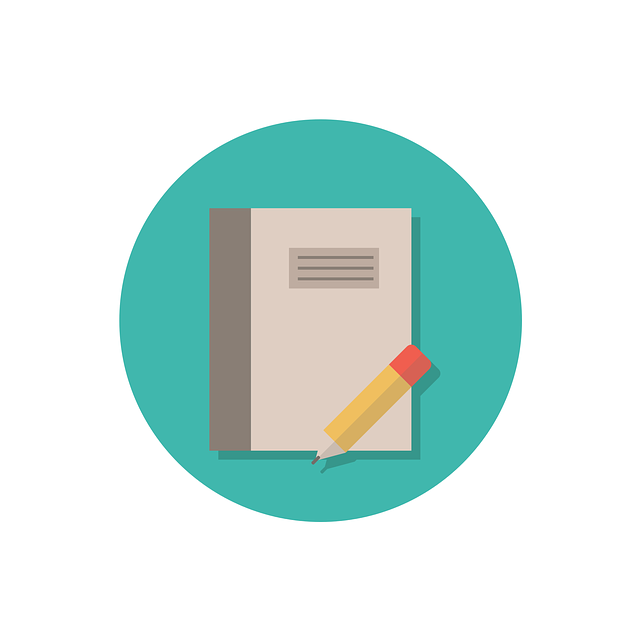
平成17年、文部科学省は家庭に引きこもりがちで十分な支援を受けられない不登校の児童生徒に対し、IT等を活用した学習活動を行うとき、定めた要項を満たした場合に出席扱いにするという方針を定めています。
引用元:すらら公式サイト
すららの出席扱い制度は、不登校や長期欠席が続く子どもが、オンライン学習を学校の出席として認めてもらうための仕組みです。
学習状況を詳しく記録し、学校へ提出することで出席扱いの判断材料になります。
制度を正しく理解すると、家庭での学びが安心につながります。

すららはオンラインで学ぶ教材ですが、出席扱い制度に対応している点が特徴です。
自宅で取り組んだ学習が学校の出席に置き換わる可能性があり、不登校の子どもや登校が難しい時期のある家庭にとっては大切な支えになります。
制度はすららが独自に決めているものではありません。
学校教育法施行規則に基づき、学校が「学習の実態」を確認できた場合に出席扱いにするかどうかを判断します。
すららはこの判断材料を整える役割を担い、保護者と学校の間をスムーズにする仕組みを提供しています。
すららが提供する出席扱い制度の仕組み
すららは学習の記録を自動で残す仕組みを持っています。
ログイン時間や学習した単元、回答履歴などが細かく保存されます。
これらの記録は学校側が「学習の実態」を判断する際に役立ちます。
すららのシステムで蓄積される主な情報は次のような内容です。
- 学習した日付
- 学習時間の合計
- 取り組んだ単元の進行状況
- 問題の正答率
- 単元ごとの理解度
数字や進行状況が記録されるため、感覚ではなく具体的な根拠として学校へ提示できます。
すららコーチと呼ばれるサポート担当者が書類の整理を手伝ってくれる場合もあり、忙しい家庭でも準備しやすい点が魅力です。
保護者が取り組む作業は学習履歴の確認と提出が中心です。
学校の先生に「すららで学んだ内容を出席扱いの資料として提出します」と伝えた後、プリントアウトした資料やPDFデータを学校へ渡す流れになります。
学校側の判断ポイントと位置づけ
学校は提出された資料をもとに、子どもの学習状況が「登校した生徒に近い状態か」を確認します。
判断する際に見られやすいポイントはいくつかあります。
- 学習が毎週のように続いているか
- 学習時間が十分に確保されているか
- 理解度が低いまま放置されていないか
- 学習内容が学校の進度とかけ離れていないか
このあたりが整っていると、出席扱いとして評価しやすくなります。
学校側は形式的な時間ではなく、子どもの“学びの実態”を重視する傾向があります。
また出席扱いの最終判断は校長が行います。
学年主任や担任の意見が基礎になる場合もありますが、学校全体の方針に基づいて承認されます。
教育委員会の指示が影響するケースもあるため、学校ごとに判断基準が違う点は理解しておく必要があります。
学習履歴の種類と提出方法
すららの学習履歴には複数の種類があります。
それぞれ役割が違うため、組み合わせて提出すると説得力が増します。
提出に使う資料は次の3種類がメインです。
- 学習ログ(自動記録)
- ユニット到達記録
- 面談・サポート記録
これらを合わせると、学校が「学習が定着しているか」を判断しやすくなります。
資料はPDFで出力できるため、保護者が手作業で作る必要は多くありません。
プリントして渡すか、メールで送付するのが一般的です。
学習ログ・ユニット到達・面談記録の違い
種類ごとの特徴を分かりやすく整理すると次のようになります。
| 種類 | 内容 | 学校が確認しやすい点 |
|---|---|---|
| 学習ログ | 学習時間や取り組み日を自動記録 | 学習の継続性 |
| ユニット到達 | 単元の理解度や完了状況 | 実際の学力の伸び |
| 面談記録 | 子どもの状況や担当コーチの所見 | 目的意識や変化 |
三つを組み合わせることで「どれくらい学びが続いているか」「理解が深まっているか」が明確になります。
学校は資料を照らし合わせながら判断するため、抜け漏れのない提出が大切です。
面談記録があると、学校側は子どもの変化をより具体的に把握できます。
特に不登校状態から少しずつ学習が再開している家庭では、気持ちの変化が出席扱い判断に有利に働く場合があります。
すららの出席扱い制度で注意すべき5つのポイント

すららで出席扱いを狙うとき、制度を理解していないと学校とのやり取りでつまずきやすくなります。
家庭側で気をつけたいポイントを知っておくと、提出の準備がスムーズに進みます。
出席扱いは簡単に見えて細かい条件があるので、最初から注意点を押さえておくと安心です。
すららの出席扱い制度は大きなメリットがありますが、注意点もいくつかあります。
制度の流れを知っておくことで、学校とのやり取りが不必要に複雑にならず、保護者の負担が軽くなります。
ここでは学校が重視するポイントや、よくあるつまずき方をまとめました。
学校との事前合意が欠かせない理由
出席扱いを成功させるには、必ず学校との相談が必要です。
学習を始めてから相談するより、開始前に合意を取っておく方が圧倒的にスムーズです。
そもそも、学校側が出席扱い制度をしっかり把握していないことも。
例えば、自宅でIT教材を使えば出席扱いの対象になることを知らない
というケースも少なくないんです。
なので、まずは学校側にコンタクトをとっておきましょう。
学校側は次のような点を確認します。
- 学習が子どもの状況に合っているか
- 学校の授業内容と大きく離れていないか
- 学習時間や内容に無理がないか
- 保護者が学習のサポートに協力できるか
これらを事前に確認してもらうことで「出席扱いの方向で進めましょう」と合意が取れやすくなります。
学校によっては「まずは2週間くらいやってみてから判断したい」と言われるケースもあります。
その場合でも、合意を取っておくと学習履歴をどのレベルまで出せば良いか分かりやすくなります。
学校への相談で避けたいのは、事後報告になってしまうことです。
「すららをやってみたので、出席扱いしてください」と伝えると、学校側は判断に困ってしまいます。

出席扱いはあくまで学校が管理する制度なので、信頼関係が大切です。
学習履歴の管理と提出で起きやすいミス
すららは自動でログを記録しますが、提出する資料は保護者がまとめます。
そのとき起きやすいミスを防ぐと、先生が確認しやすくなります。
よくあるミスは次の3つです。
- 期間が途中で抜けている
- ログの画面を複数まとめずバラバラで提出する
- ユニット到達記録を出し忘れる
特に多いのは、学習が続いていてもPDFのファイルが途中で途切れているケースです。
学校側は「毎日どれくらい取り組んだか」を確認するため、抜けていると評価が難しくなります。
提出のコツは、月単位で資料をまとめることです。
1か月まとめて1冊の資料にすると、先生も確認しやすく、家庭側も管理が楽になります。
学習量や条件の確認が必要な背景
学校は出席扱いにするとき、一定の学習量があるかを確認します。
ただし「1日何時間必須」と決められているわけではありません。
子どもの状態や学年に合わせて柔軟に判断されます。
目安としては、
- 週に数回の学習があること
- 単元を継続して進めていること
- 理解度が低いまま放置されていないこと
このあたりが確認される傾向があります。
理由は、出席扱いは単なる出席数ではなく、学習の実態を重視する制度だからです。
「家にいるだけ」では出席扱いにならず、「家で学んでいる事実」が必要になります。
家庭としては無理のない学習計画を立てる方が続きやすく、出席扱いの判断にも好影響です。
すららのサポート範囲と学校判断の差
すららはログの記録や教材提供を行いますが、出席扱いを決めるのは学校です。
ここを勘違いしやすく、学校とのやり取りで戸惑う家庭もあります。
例えば、
- すらら側は出席扱いを前提にサポートしてくれる
- けれど学校は全員を出席扱いにするわけではない
というケースが起こり得ます。
学校の方針や校長の判断が大きく影響するため、同じ学習量でも「認める学校」と「認めない学校」があります。
すららコーチのアドバイスは参考になりますが、最終判断は学校なので、柔軟に対応する姿勢が大切です。
契約や料金で気をつける点
すららの出席扱いは教材の通常契約の中で利用できますが、家庭の負担として考えておきたいポイントもあります。
- 契約プランは学年によって変わる
- 兄弟利用で割引が使える
- 休会はできるが、条件がある
- 解約は手続きタイミングに注意
特に注意したいのが「休会は短期間のみ」という点です。
出席扱いの提出期間が続くときに休会してしまうと、ログが止まってしまい判断材料が減ります。
料金面では、長く続ける可能性があるなら年間契約の方がコストを抑えられます。
無理に続ける必要はありませんが、計画的に考えた方が負担が軽くなります。
出席扱いにつながる学習履歴の作り方と見せ方
出席扱いを目指す場合、学校が確認しやすい形で学習記録をまとめ、必要な資料をそろえることが欠かせません。
ここでは「どんな学習履歴が提出向きか」「どう見せると学校に伝わりやすいか」を分かりやすく紹介します。
すららは学習履歴が自動で残る仕組みがそろっているため、出席扱いの条件と相性が良い教材です。
ただし、学校によって求める資料が違うため、提出する際には工夫が必要になります。
ここでは、家庭で作れる学習履歴の管理方法から、学校に提出する際のまとめ方まで詳しく整理していきます。
自動ログ・手動メモ・面談記録の活用法
すららの学習履歴は、大きく3つに分けられます。
- 自動ログ(システムが生成)
- 手動メモ(保護者・子どもが書く)
- 面談記録(コーチとのやりとり)
これらは使い分けることで、学校に提出する資料に厚みが出ます。
● 自動ログ
すららが自動で保存してくれるログで、学習の証拠としていちばん使いやすい資料です。
ログに含まれる情報は次のとおりです。
- 学習日時
- 学習時間
- 進んだ単元
- 到達したユニット
- 正答率
学校は「自宅でどれくらい学習しているのか」を客観的に判断したいため、数字で示せる自動ログは重要な資料になります。
● 手動メモ
自動ログだけでは伝わらない部分を補う資料です。
- なぜその単元に取り組んだのか
- 子どものつまずきポイント
- 取り組みながら気づいたこと
- 当日の体調や様子
家庭で気づいた視点をメモしておくと、学校が判断しやすくなります。
短文でも効果があるので、毎日少しずつ残しておくと負担も少なくなります。
学校が求める提出資料のまとめ方
学校側は提出された資料を元に、出席扱いの判断をします。
判断しやすい形にまとめると、話し合いもスムーズに進みます。
資料をまとめるときの流れを紹介します。
● ① 月ごとのログを1つにまとめる
すららのログは詳細ですが、そのまま出すと量が多くなりがちです。
月ごとにまとめたPDFやスクリーンショットを提出すると見やすくなります。
● ② 到達ユニットを一覧化する
到達したユニットをリスト化すると、子どもの理解度がひと目で分かります。
学校の先生にとっても確認しやすい資料です。
● ③ つまずきポイントや成功体験を短くまとめる
学校は「家庭でどのように学び、どんな変化があったのか」を知りたがります。
短い文章で構わないので、学習の振り返りを添えると評価が高くなりやすいです。
例:
- 図形の問題が難しく、スモールステップで進めた
- 読解の問題をゆっくり解いたら自信がついた
- 集中が続かない日は学習時間を短くした
感想レベルでも十分なので、家庭の状況を具体的に伝えましょう。
● ④ コーチとの面談内容をまとめる
面談内容の要点を箇条書きで添えると、家庭の取り組みが伝わりやすくなります。
- コーチと作成した今月の目標
- 苦手単元の克服方法
- 子どもの変化
学校は「計画的に学習しているか」を判断するため、面談記録は非常に有効です。
学習ログの信頼性を高めるポイント
提出資料の信頼性を高めるために、家庭で工夫できるポイントがあります。
● ログの偏りをなくす
同じ単元ばかり学ぶと、「本当に学力が身についているのか?」と学校が疑問に感じることがあります。
バランスよく学ぶことが、出席扱いにつながりやすいです。
● 学習時間が極端に短すぎないようにする
毎日5分だけでは、学校側が「出席扱いに対応している」と判断しづらくなります。
短くても15〜30分の学習を重ねると説得力が出ます。
● ログとメモをセットで残す
ログには数字しか残らないため、保護者のメモを添えると信頼性が上がります。
数字と文章の両方があると、学校側が判断しやすい資料になります。
提出前チェックリスト
提出前に確認しておくと便利なチェックリストを紹介します。
- 月ごとの学習ログをまとめたか
- 到達ユニットの一覧を作ったか
- 子どもの学習ペースを説明するメモを添えたか
- 面談記録をまとめたか
- 家庭で気づいたポイントを短文で記載したか
- 学校が求める資料の形式(紙/PDF)を確認したか
これらがそろっていれば、出席扱いの相談をスムーズに進められます。
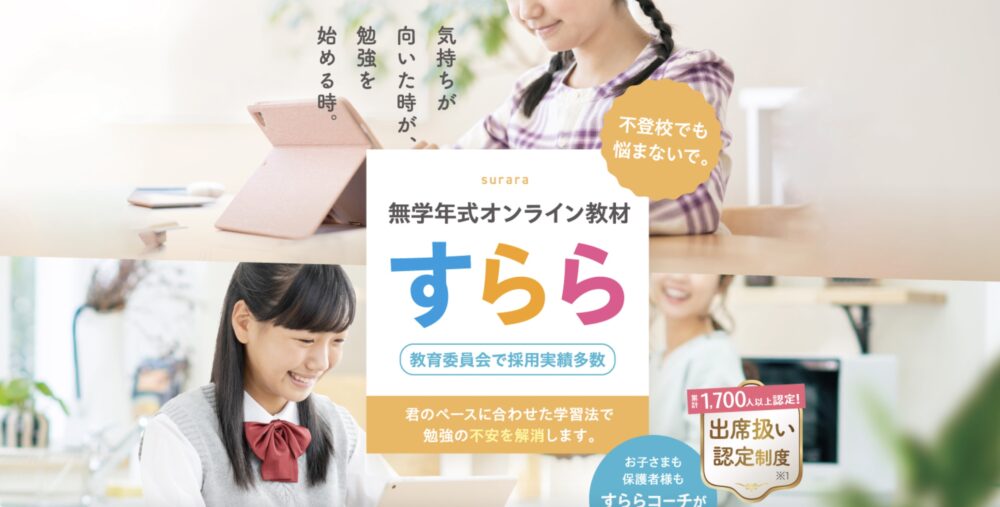
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えます。
すららで出席扱い(ネット出席)をしましょう。
すららの強みと得意領域(出席扱いとの相性)
すららは多くのオンライン教材の中でも、出席扱いとの相性が特に良いと言われています。無学年式の構造や対話型の学習システム、コーチのサポートがその理由です。
ここでは、すららの強みを「出席扱いに向いている視点」で分かりやすく紹介します。
すららの特徴をひと言でまとめると、「自宅での学習を学校に伝えやすい教材」です。
一般的なタブレット教材は単元の確認テストだけで進んでいく構造が多いですが、すららは学習ログの細かさや授業の流れが学校の評価基準と一致しやすい設計になっています。
ここでは、すららが持つ独自の強みを具体的に紹介します。
無学年式の学び直しが強い理由
すららは学年にしばられない「無学年式」の教材です。
これは、特に不登校の子どもや、学校の授業から一時的に離れている子どもと相性が良いポイントになります。
● 無学年式が出席扱いと相性の良い理由
- 学校の進度に合わせられなくても、理解度に合わせて学習できる
- 得意な教科を先に進められる
- 苦手単元を学年をまたいで学び直せる
- 学校の授業から離れていても、基礎学力を取り戻しやすい
「今は○年生だから、この単元をやらなければならない」という縛りがないため、無理がかかりません。
不登校期間が長くなると、教科書の内容をいきなり追うのは難しくなります。
すららは最もつまずいた地点まで戻って学び直せるため、出席扱いの判断材料としても評価されやすい教材です。
対話型教材で学習の質を高めやすい点
すららの大きな特徴のひとつが「対話型授業」です。
画面上で先生役のキャラクターが子どもの理解に合わせて説明し、質問に答えてくれます。
● 対話型の良さ
- 動画を見るだけの教材と違い、学習の参加姿勢が自然に生まれる
- 例題と解説がセットで進むため、理解の流れが途切れにくい
- 苦手な問題にはヒントが段階的に入る
- 正答だけでなく、思考過程を意識できる
学校側が重視するのは「その子が家で理解を深められる構造になっているか」です。
すららは理解のステップを可視化しやすいため、出席扱いの判断で評価されやすくなります。
サポート体制の強み(コーチ・保護者画面)
すららは教材だけでなく、「保護者のサポート環境」がしっかり作られています。
● すららコーチの役割
すららコーチは、子どもの学習状況を見ながらアドバイスをくれる担当者です。
- 学習計画を一緒に作る
- 苦手の改善方法を提案する
- 進み具合を定期的に確認する
- 子どもの様子を見ながら声かけをくれる
家庭だけで進めると行き詰る場面がありますが、コーチが入ることで継続しやすい流れができます。
● 保護者画面の「見える化」が強い
保護者画面では細かいログが一覧で確認できます。
- 何の単元を、いつ、どれくらい学習したか
- 正答率の変化
- 到達ユニット
- つまずきポイント
学校側へ提出する資料の基礎になる部分なので、保護者画面は出席扱いの強い味方です。
出席扱いとの相性が良い理由をまとめると
すららが学校の出席扱い制度と相性が良いのは、以下の理由が大きいです。
- 学習ログが細かく記録される
- 無学年式でつまずいた単元から学べる
- 対話型で「理解している様子」が伝わりやすい
- コーチのサポートが家庭の学習を支える
- 保護者画面で提出用資料が作りやすい
学校が知りたい情報と、すららが提供する情報が一致しているため、出席扱いの判断材料になりやすい教材です。
すららが向いている人・向かない人

すららは幅広い学年に対応できますが、全員に向くわけではありません。
学習スタイルや家庭の状況によって、相性の良し悪しがはっきり出る教材です。
ここでは、すららが向くケースと向かないケースを整理しながら、他の選択肢も合わせて紹介します。
すららは不登校の子どもや、勉強の遅れに悩む家庭から高く評価されています。
無学年式で、ゆっくり学び直せる点が安心材料になっているからです。
ただし、向き不向きはどの教材にもあり、すららも例外ではありません。
ここでは、実際の利用者が感じた相性の違いをわかりやすくまとめます。
すららが向いているケース
すららが向くのは「自分のペースで理解を深めたいタイプ」や「学校に行けない期間でも学力をキープしたい子ども」です。
● 不登校・別室登校・保健室登校の子ども
学校に行けない期間が続くと、授業の進度から離れてしまい、戻りにくくなります。
すららは無学年式なので、遅れの心配をせずに学び直せます。
- 学校が進んでも焦らない
- 自分の理解レベルから始められる
- ゆっくり取り組める
出席扱い制度とも相性が良く、学校と連携しやすい点も大きなメリットです。
● コツコツ型の学習が苦手な子
多くの教材は「進めるだけで終わる」ケースが起きますが、すららは理解を深める流れを作りやすい教材です。
対話形式で「なぜそうなるのか」を説明してくれるので、ぼんやりした理解を避けやすくなります。
● 基礎からつまずいている子
算数や国語のつまずきは、学年をまたいでいる場合が多いです。
すららは小学校の内容まで戻れるため、積み残しを解消しやすい教材です。
● 保護者が勉強を教えるのが難しい家庭
「教えたいけれど、教え方がわからない」
という悩みを持つ家庭は多いです。
すららコーチの存在が背中を押してくれるため、親の負担を減らしながら学習習慣を作れます。
すららが向かないケース
すららにも弱点があり、合わないケースがあります。
● ゲーム性が強い教材を求めている子
すららは、派手なアニメーションや報酬システムが多いタイプではありません。
学習中心なので、刺激の強いゲームアプリになれている子どもだと物足りなく感じる場合があります。
● 自分でタブレットを開く習慣がない子
すららは「自分でログインして、学習を始めること」が重要になります。
保護者の声かけが必要になる家庭も多く、完全に放置できる教材ではありません。
● 紙の教材や書き込み中心の学習を優先したい場合
すららはデジタル教材の比率が高いため、紙教材で書き込みたいタイプの子どもとは相性が分かれます。
● 高校受験のハイレベル対策だけをしたい家庭
基礎の積み上げは強いですが、難関高校向けの応用レベルは別教材が必要です。
他の選択肢(フリースクール・教育委員会の相談)
すららが合わない場合でも、不登校支援には複数の選択肢があります。
● フリースクール
学校に行けない子どものために作られた民間の居場所で、学習支援や生活支援が受けられます。
「対面での関わり」が必要な子には良い選択肢です。
● 教育委員会の適応指導教室
無料で通える公的な支援で、学習や人間関係のサポートが受けられます。
すららと併用する家庭も多いです。
● 家庭教師・オンライン個別指導
「わからない部分をピンポイントで解決したい」場合に向いています。
すららの弱点を補う手段として使う家庭もあります。
向いている家庭・向かない家庭のまとめ
すららが特に合う家庭は以下のタイプです。
- 子どもが学校に行けない期間が続いている
- 学び直しが必要
- 細かい学習ログが必要
- 親のサポートが難しい
- 出席扱い制度を活用したい
反対に相性が不安な家庭は、
- 刺激の多いアプリを求めている
- 紙中心の勉強が合う
- 自主性のある学習が苦手
- 難関校向けの応用を最優先したい
などの場合です。
向き不向きを知っておくと、導入後のミスマッチを避けられます。
まとめ:すららの出席扱い制度を正しく活用するために
すららの出席扱い制度を使うと、不登校の子どもの負担が減り、学校との接点を保ちやすくなります。
学習ログの整理や学校への説明方法を理解しておけば、スムーズに認められやすくなります。
ここでは記事全体のポイントと、学校相談にそのまま使える手順を整理してまとめます。
すららを出席扱いとして使いたい家庭は、制度の流れと注意点を理解しておくと混乱しにくくなります。
学校の判断基準は文科省の通知によって決まっていますが、実際の判断は学校や担任によって違います。
そのため、学習ログを丁寧に整えたり、事前の相談を行ったりする準備は欠かせません。
ここまでの内容を整理すると、すららの出席扱い制度は「仕組みを理解して、学校とのコミュニケーションを整えれば進めやすい制度」と言えます。
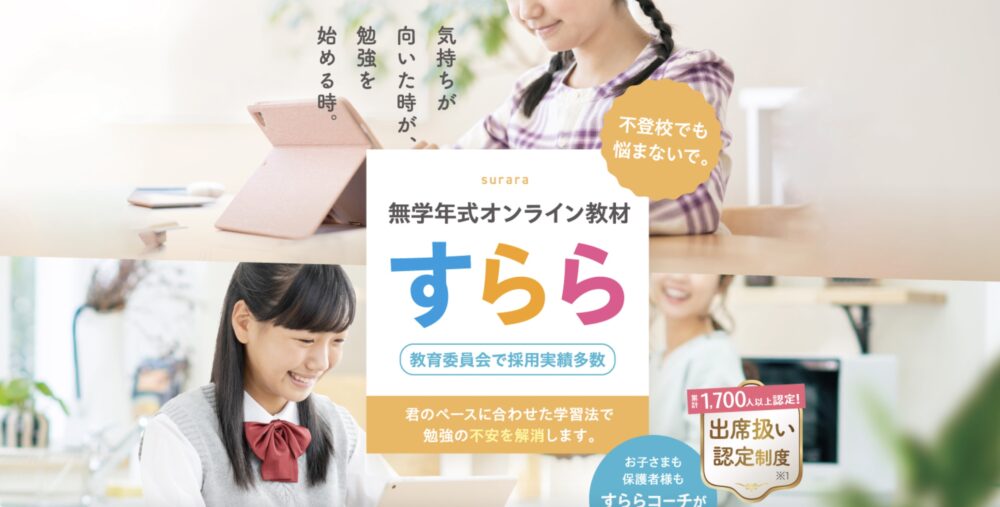
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えます。
すららで出席扱い(ネット出席)をしましょう。