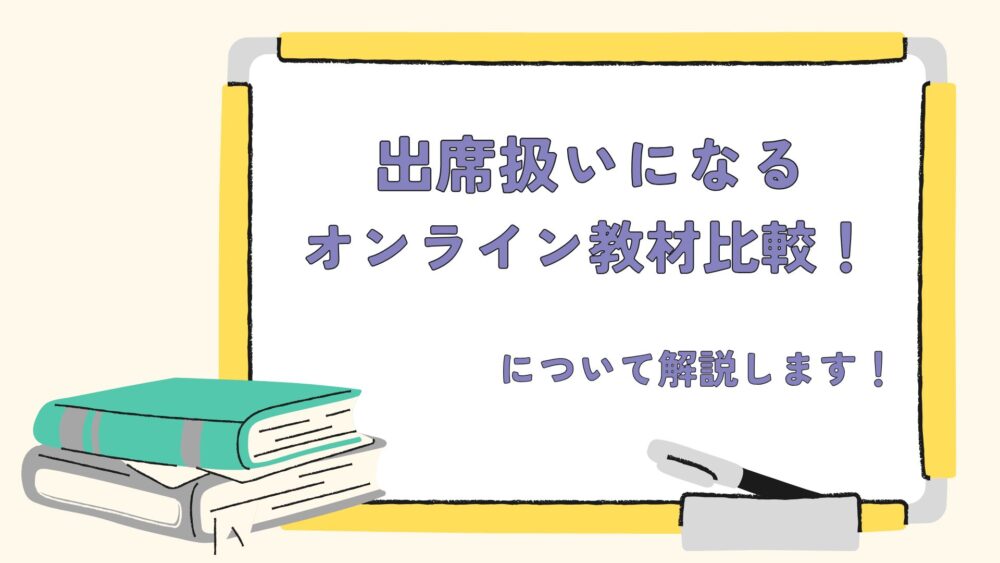「不登校オンライン教材比較で出席扱い対応の教材を知りたい」
「家庭教師より費用が抑えられる教材を探している」
「授業に遅れず続けられるオンライン教材を比較したい」
不登校の子どもに合う教材を探すのは情報が多くて悩みやすいですよね。
不登校オンライン教材を選ぶ際には、出席扱い制度への対応、学習内容の質、サポート体制を比較することが大切です。
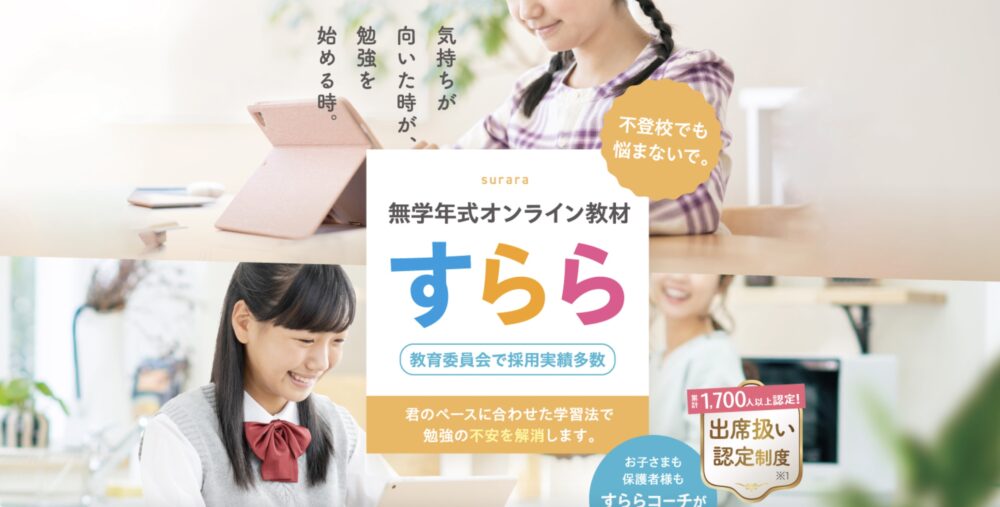
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。
まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!
\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/
不登校向けオンライン教材比較のポイント
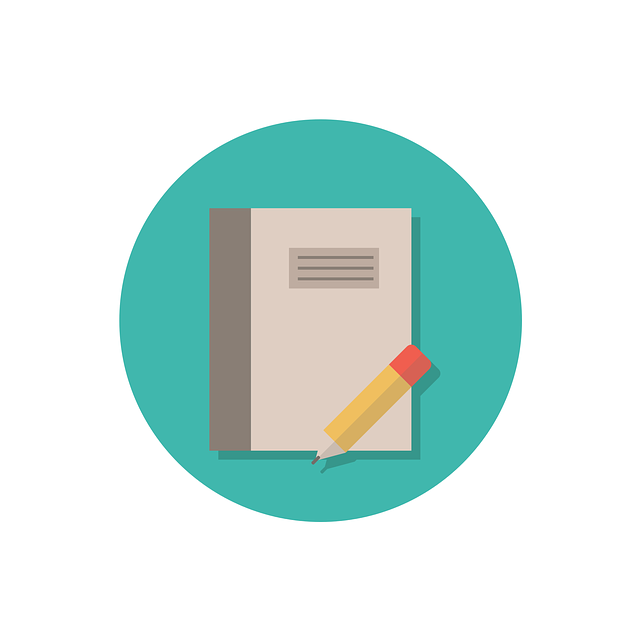
不登校の子どもに合うオンライン教材を選ぶとき、保護者は多くの情報に迷いやすくなります。出席扱い制度に対応しているかどうか、教材の形式、学年や教科への対応範囲、保護者サポートの有無など、比較する観点を整理しておくことが大切です。ここでは教材選びで押さえるべき重要なポイントを紹介します。
出席扱い制度に対応しているか
不登校の子どもにとって、出席扱い制度は学習だけでなく進級や内申点に関わる大切な仕組みです。文部科学省は、不登校の児童生徒がオンライン教材やICTを活用した学習を行う場合、一定の条件を満たせば「出席」と認められる制度を設けています。
この制度を利用するには、
- 学校長の判断
- 学習内容が学校の授業に準じているか
- 担任や学校との連携があるか
などの条件をクリアする必要があります。出席扱いに対応している教材であれば、学校との調整もしやすく、安心して学習を続けることができます。教材を比較するときは、公式に「出席扱いに利用可能」と明記されているか、実際に利用実績があるかを確認することが重要です。
教材の形式(動画授業・AI教材・家庭教師型)
オンライン教材には大きく分けて3つの形式があります。
- 動画授業型
録画された授業やライブ授業を通じて学ぶ形式です。学校の授業に近い形で学べるため、学習の抜けを補いやすい特徴があります。授業に参加している感覚を得やすいため、不登校で孤立感を持つ子どもに合う場合があります。 - AI教材型
AIが学習状況を解析し、つまずきやすい部分を重点的に出題してくれる仕組みです。個別最適化された学習ができるため、学年をまたいだ復習や先取りが可能になります。自分のペースで進めたい子どもには向いています。 - 家庭教師型オンライン授業
講師と1対1で学習を進める形式です。個別指導のため理解度に合わせた説明を受けられ、学習以外の悩みにも寄り添ってもらえる場合があります。ただし、費用が高くなりやすい点は注意が必要です。
このように形式ごとに特徴が異なるため、子どもの性格や学習習慣に合わせて選ぶことが欠かせません。
対応学年と教科数の違い
オンライン教材によって、対応できる学年や教科の範囲は大きく変わります。
- 小学生から高校生まで幅広く対応している教材
- 国語・算数・英語に特化した教材
- 苦手教科の克服に力を入れた教材
など、それぞれの強みがあります。
特に不登校の子どもは、学年をさかのぼって学び直すケースが多くあります。そのため、学年に縛られず利用できる「無学年方式」の教材は非常に有効です。また、主要教科に加えて理科や社会もカバーしている教材なら、高校受験を見据えた学習も可能になります。
保護者サポートの有無
不登校の子どもが学習を継続するには、保護者のサポートが大きな役割を果たします。しかし、保護者が常に勉強を見てあげるのは難しいのが現実です。
そこで重要なのが、教材がどれだけ保護者を支援してくれるかという点です。例えば、
- 学習状況を自動でレポートしてくれる機能
- 担任やコーチが定期的にフォローしてくれる仕組み
- 保護者向け相談窓口の有無
といったサポート内容があると、家庭の負担が減り、安心して任せることができます。
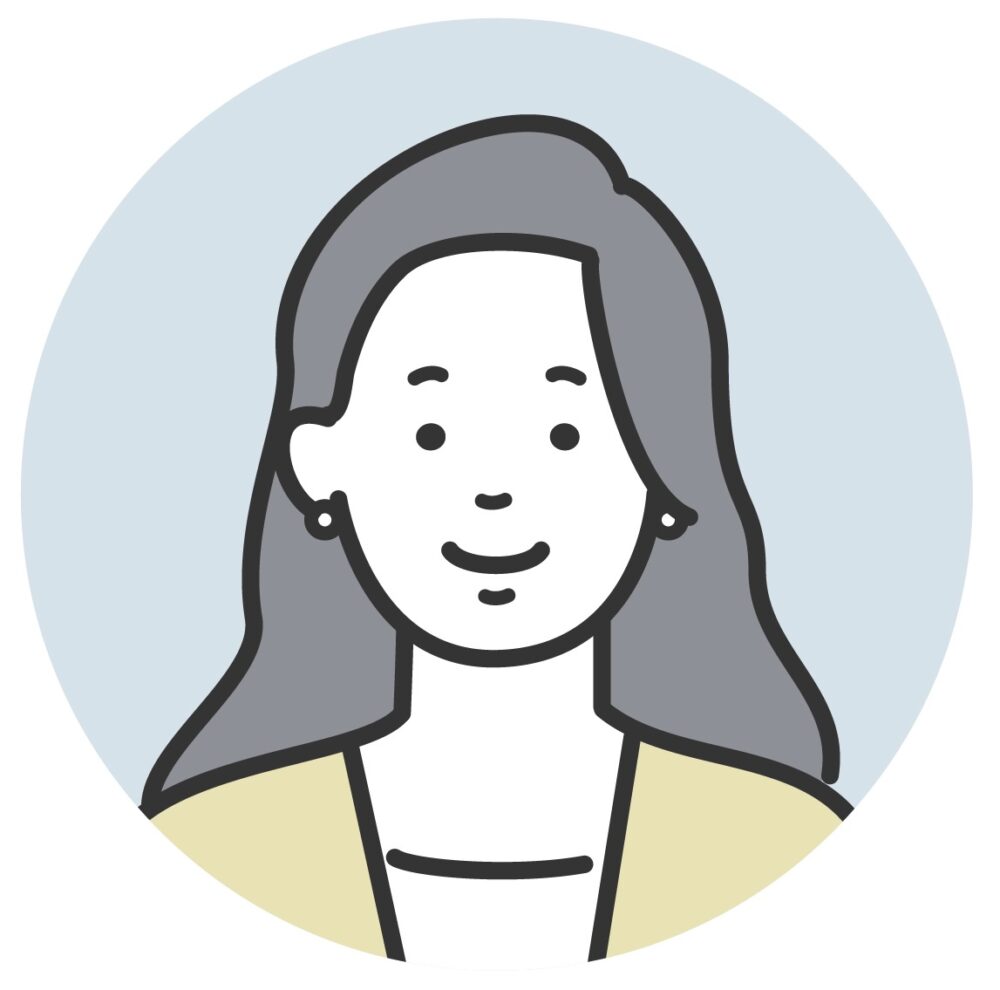
教材選びでは「子どもに合うかどうか」だけでなく「家庭で無理なく続けられるか」を見極めることが大切です。
不登校オンライン教材と出席扱い制度(文科省の基準)
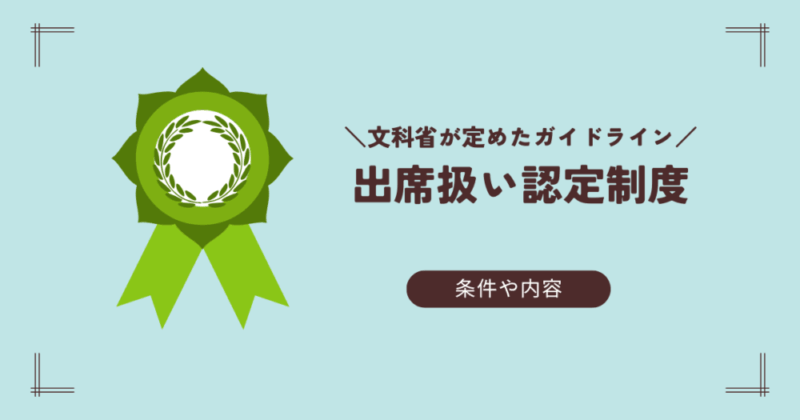
不登校の子どもが安心して学習を続けるためには、学びを評価される仕組みが欠かせません。その一つが「出席扱い制度」です。文部科学省は、不登校の子どもが自宅でICTやオンライン教材を使って学習した場合、一定の条件を満たせば学校の出席と認める制度を整備しています。この制度を理解しておくことで、教材選びの基準が明確になります。
出席扱い制度の概要
出席扱い制度とは、不登校の子どもが学校以外で学習をしても、条件を満たせば出席日数として認められる仕組みです。内申点や進級、進学に関わるため、保護者にとって重要なポイントとなります。
文科省が示す条件には、以下のようなものがあります。
- 学校長が適切と認めること
- 学校の授業に相当する内容であること
- 教材を使った学習の進捗が確認できること
- 担任や学校との連携が図られていること
これらを満たすことで、家庭での学習が正規の出席として扱われる可能性があります。
出席扱い制度に対応している教材の特徴
出席扱いに対応しているオンライン教材は、いくつか共通する特徴があります。
- 学習ログが自動で記録され、学校に提出できる
- 教材提供会社が学校と連携した実績を持っている
- 学習内容が学校の教科書に準拠している
- 学習の進度や成果をレポート形式で出せる
こうした仕組みが整っている教材は、出席扱いとして認められやすくなります。特に、学校への報告書を自動生成できる機能を備えた教材は、保護者にとっても大きな負担軽減につながります。
学校との連携が不可欠
出席扱い制度を利用するには、教材だけでなく学校との関係づくりも大切です。制度はあくまで「学校長の判断」に基づくため、担任や校長に相談し、連携を取りながら進める必要があります。
保護者ができる具体的な行動としては、
- 学校に制度の存在を伝える
- 利用予定の教材が出席扱いに対応していることを資料で提示する
- 学習の進度や成果を定期的に共有する
などが挙げられます。学校と協力体制を築くことで、子どもが安心して学習に取り組める環境が整います。
制度を活用するメリットと注意点
出席扱い制度を利用することで得られるメリットは大きいです。
- 不登校による欠席日数の不安が軽減される
- 学校への復帰がスムーズになる
- 内申点や進級に影響しにくくなる
一方で注意点もあります。制度を利用しても、必ずしもすべての学校が認めるわけではありません。また、制度に対応していない教材も多く存在します。保護者が「出席扱いに利用できるか」を事前に確認する姿勢が欠かせません。
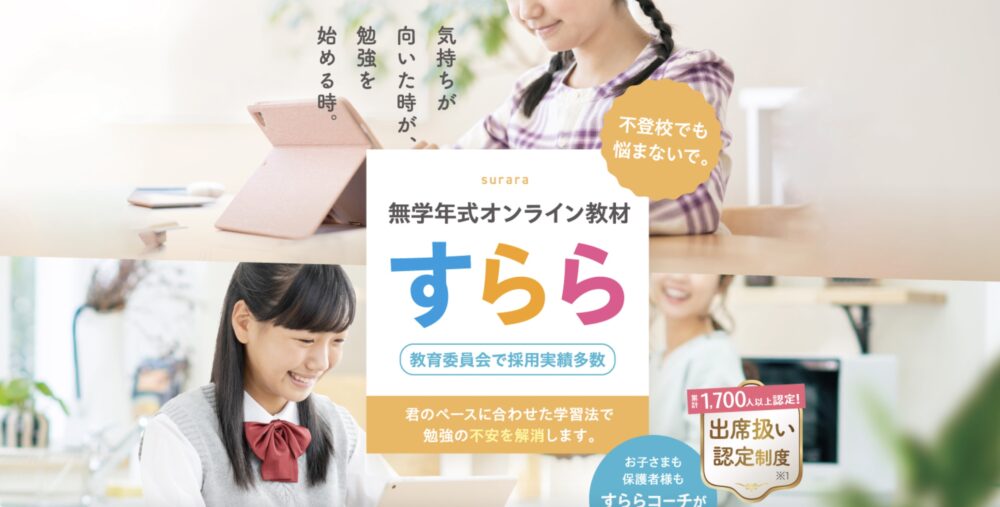
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。
まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!
\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/
オンライン家庭教師と教材の違い
不登校の子どもにとって、自宅での学習手段は大きく「オンライン家庭教師」と「オンライン教材」に分かれます。どちらも学校に通えない子どもの学習支援に役立ちますが、仕組みやサポート内容、費用感には違いがあります。違いを理解することで、子どもに合った選択がしやすくなります。
オンライン家庭教師の特徴
オンライン家庭教師は、講師がリアルタイムで子どもに授業を行うサービスです。パソコンやタブレットを使い、ビデオ通話を通じて学習を進めます。
メリットとしては、
- 個別指導なので理解度に合わせた進め方ができる
- 学習だけでなく精神的なサポートも受けやすい
- 質問や疑問をその場で解決できる
といった点があります。特に不登校の子どもは、勉強と同時に気持ちの支えが必要なケースが多いため、講師との対話が安心感につながります。
一方でデメリットは、
- 授業料が高額になりやすい(月2〜4万円程度が相場)
- 講師の質に差がある
- 子どもがその時間に参加できないと授業が進まない
といった点が挙げられます。費用や相性の見極めが重要になります。
オンライン教材の特徴
オンライン教材は、AI学習や映像授業などを利用して、自分のペースで進められる学習システムです。家庭教師に比べて費用が抑えられる傾向があります。
メリットとしては、
- 料金が比較的安い(月額3000〜8000円程度が多い)
- 24時間いつでも利用でき、生活リズムに合わせやすい
- 教材によってはゲーム感覚で学習できる
- 学習ログが残るため、出席扱い制度に対応しやすい
などがあります。時間や費用面で柔軟性が高いのが特徴です。
一方でデメリットは、
- 子どもが自発的に取り組まないと進まない
- 学習習慣が身についていない場合は継続が難しい
- わからない部分をすぐに質問できない場合がある
といった点です。子どもの性格や習慣に合わせて選ぶことが求められます。
どちらが不登校の子に向いているか
オンライン家庭教師と教材、どちらが向いているかは子どもの状況によって変わります。
- 「人とのやり取りで安心感を得たい」→オンライン家庭教師が向いている
- 「自分のペースでコツコツ進めたい」→オンライン教材が合いやすい
- 「費用を抑えつつ学習効果も重視したい」→オンライン教材が候補になる
家庭の予算、子どもの学習意欲、サポートの必要度を考慮して選ぶことが大切です。場合によっては、両方を組み合わせる方法も選択肢となります。
不登校の子に合う教材の選び方
不登校の子どもに教材を選ぶ際は、学校の補習という視点だけでなく、子どもの気持ちや生活リズムに寄り添った基準が重要になります。教材が合わないと継続できず、学習意欲の低下につながるため、選び方のポイントを整理しておきましょう。
学習の目的を明確にする
まず考えるべきは「教材を使う目的」です。
- 学校の授業に追いつくことが第一の目標なのか
- 学習習慣をつけることを重視するのか
- 出席扱い制度を利用して、学校に復帰しやすくしたいのか
目的によって選ぶ教材は変わります。たとえば、定期テストの対策を重視するなら教科書準拠型、基礎学力の定着を目指すなら無学年方式の教材が適しています。
子どもの性格や学習スタイルに合うか
不登校の子どもは、学習意欲や集中力に差が出やすいです。そのため教材が子どもの性格に合うかどうかが大きなポイントになります。
- ゲーム感覚で学べる教材 → 勉強への抵抗感が強い子に向く
- 動画授業型 → 先生の説明で理解したい子に合いやすい
- AI型学習 → 自分のペースで着実に進めたい子に適している
教材のタイプを理解し、子どもの「取り組みやすさ」を優先することが継続につながります。
保護者の負担を考える
教材を選ぶ際は、保護者のサポート負担も考慮すべきです。
- 親が進捗管理しなければならない教材は、負担が大きくなりやすい
- 自動で学習管理や復習を提案してくれる教材は保護者のサポートが少なくて済む
- 学習相談ができるサポート窓口があると安心
家庭の状況によっては、保護者がつきっきりにならなくても続けられる教材を選んだ方が良いケースもあります。
出席扱い制度に対応しているか
不登校の子どもにとって、出席扱い制度は大きな支えになります。文科省の定める要件を満たしている教材であれば、学校と連携して出席扱いを認めてもらえる可能性があります。
具体的には、
- 学習記録が残るシステムがある
- 学校と教材提供側が連携できる仕組みがある
- 保護者と学校が協力して運用できる
こうした条件を満たす教材を選ぶことで、学習だけでなく学校生活への復帰もしやすくなります。
費用と継続性を重視する
教材は数ヶ月単位で利用することが多いため、費用の継続性も重要です。家庭教師に比べれば安価ですが、教材によって料金差はあります。
- 月額3000〜8000円 → オンライン教材の一般的な相場
- 月額1万円以上 → サポートが手厚い教材や家庭教師型に多い
短期的に高額な教材を導入しても、継続できなければ効果が薄くなります。家庭の予算に合ったものを長期的に利用するのが理想です。
不登校向けオンライン教材の比較ポイント
不登校の子どもにオンライン教材を導入する場合、どの教材が子どもに合うか判断することが重要です。教材の種類や特徴を理解し、比較の視点を押さえることで、学習の効果や継続のしやすさが変わります。ここでは比較時に確認すべきポイントを整理します。
学習形式と授業スタイル
オンライン教材には大きく分けて次の学習形式があります。
- 映像授業型:授業動画を視聴し、理解度に応じて自習を進める
- AI型学習:学習履歴や正答率に応じてカリキュラムが自動調整される
- ゲーム・アプリ型:ゲーム感覚で問題を解きながら学習する
子どもが飽きやすい場合は、学習形式が柔軟で、楽しみながら学べる教材を選ぶと継続しやすくなります。
教科と対象学年の対応
教材ごとに対応教科や学年の幅が異なります。
- 全教科対応:国語・算数(数学)・理科・社会などをまとめて学習できる
- 教科限定型:苦手教科や学習の遅れが気になる分野に特化
- 学年無学年型:学年に縛られず、子どもの理解度に応じて先取り・復習が可能
不登校の子どもは学習の遅れや得意不得意の差があることが多いため、学年無学年型教材は特に有効です。
出席扱い制度への対応
前の章で触れた出席扱い制度は、教材選びの大きなポイントです。
- 学習履歴やレポートが自動で作成できるか
- 学校に提出可能な形式か
- 教師や保護者が進捗を確認できるか
これらの条件を満たす教材であれば、学校との連携がスムーズになり、制度活用のハードルを下げられます。
講師のサポート体制
オンライン教材によっては、個別指導や家庭教師のサポートが付いているものがあります。
- 講師が学習内容をチェックして指導してくれる
- チャットやビデオ通話で質問できる
- 学習のモチベーション維持に関与してくれる
サポート体制がしっかりしている教材は、子どもがつまずいたときに安心です。
料金とコストパフォーマンス
オンライン教材は月額制や年間一括制など料金体系が異なります。比較の際は、次の視点が重要です。
- 月額料金と年間合計の負担
- 教材の追加費用やオプション料金
- 料金に対する学習内容やサポートの充実度
コストと学習効果を総合的に比較し、家庭の予算に無理なく取り入れられる教材を選ぶことが大切です。
実際の口コミや体験談
教材選びでは、利用者の声を参考にすることが有効です。
- 子どもが学習を続けやすかったか
- 苦手科目の克服や学習意欲の向上に役立ったか
- 学校との連携や出席扱いの実績はあったか
口コミや体験談を確認することで、教材の実態や家庭での取り入れやすさを把握できます。
おすすめオンライン教材3選と特徴

不登校のお子さま向けに利用できるオンライン教材は数多くあります。その中でも、出席扱いの実績や学習継続のしやすさ、家庭へのサポート体制が整っている教材を3つ取り上げて紹介します。
1. すらら
「すらら」は、不登校支援の分野で特に実績がある無学年式オンライン教材です。
- 文部科学省が定める出席扱いの条件に対応し、全国で1200名以上が利用実績あり
- 無学年方式で苦手をさかのぼり、得意は先取り可能
- AIが自動でつまずきを分析し、効率的に復習できる
- ゲーム感覚のレッスンで集中力を維持しやすい
- 「すららコーチ」が保護者や学校との連携を支援
不登校の子どもが学校復帰へつなげるステップとして活用しやすい教材です。
2. スタディサプリ
「スタディサプリ」は、リクルートが提供する動画学習サービスです。
- 小1から高3まで幅広い教科を網羅
- プロ講師による動画授業を何度も視聴できる
- 月額2,000円台と低価格で利用可能
- 主要5教科に対応し、定期テスト対策や受験学習にも強い
ただし、出席扱い制度への対応は限定的で、学習履歴の共有などは保護者がフォローする必要があります。
3. デキタス
「デキタス」は、小中学生向けの教科書準拠型オンライン教材です。
- 学校の授業と同じ内容をアニメーションで解説
- 学習履歴やレポートが残せるため、出席扱い制度に対応しやすい
- 1回10分程度の短い単元で、集中しやすい設計
- 月額3,000円台と利用しやすい料金設定
教科書ベースのため、学校に戻った時も授業にスムーズに参加できるのが強みです。
3つの教材の比較ポイントまとめ
- すらら:不登校支援の実績が豊富。AI学習・無学年制で柔軟に対応。
- スタディサプリ:低価格&動画授業が強み。ただし出席扱いには不向き。
- デキタス:教科書準拠で学校復帰しやすい。出席扱いにも対応可能。
それぞれの教材には特徴があり、お子さまの学習状況や目的に応じて選ぶことが大切です。
特に「すらら」は、無学年制でお子さまのペースに合わせられ、全国で多くの出席扱い実績もあるため、安心して導入できる教材です。
教材選びに迷ったときは、まずは体験や資料請求を利用し、子どもが続けやすいかどうかを見極めてみてください。家庭と学校の橋渡しとなる教材を選ぶことで、学びの遅れを補い、未来への選択肢を広げることにつながります。
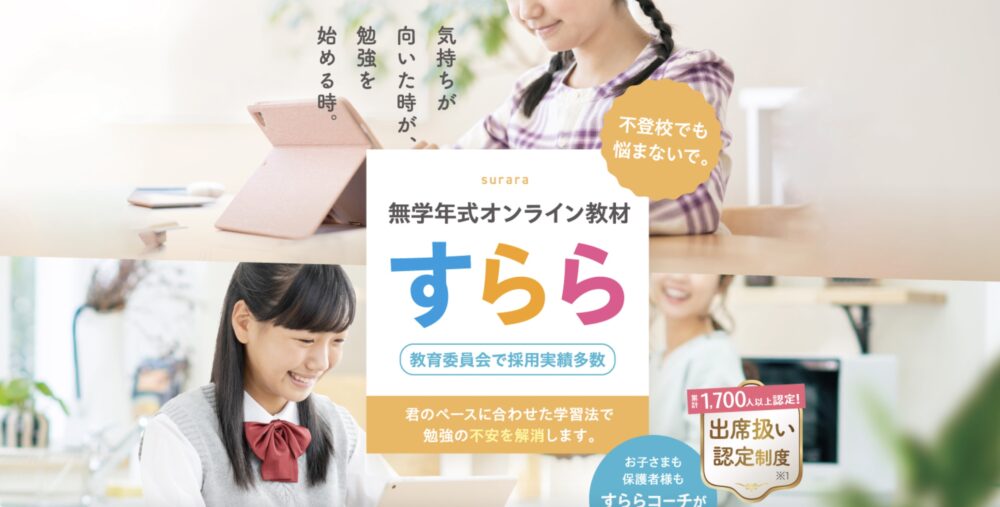
お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。
まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!
\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/